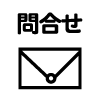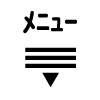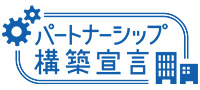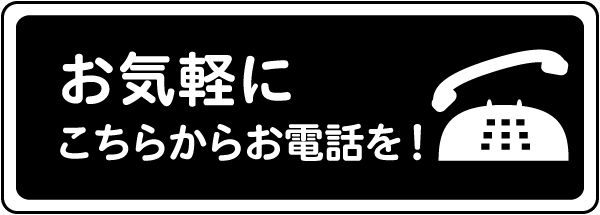「ブログを頑張って書いているのに、全然上位表示されない…」
「昨日まで上位だったのに、今日見たら圏外になっていた…」
ブログやWebサイトを運営している方なら、誰もが一度はこんな経験をしたことがあるのではないでしょうか?
Googleの検索順位って、一体どうやって決まっているんだろう?どうして急に変動するのだろう?
今回は、そんな素朴な疑問にお答えするため、Google検索順位の決まり方と変動のタイミングについて分かりやすく解説していきます。
そもそも、Googleはなぜ順位を決めるの?
まず、大前提として知っておいてほしいのが、Googleが検索順位を決める一番の目的です。
それは「ユーザーにとって最も役立つ情報を、一番見つけやすい場所に表示する」ことです。
例えば、「カレーライス レシピ」と検索した人がいます。この人は、美味しいカレーの作り方を知りたいと思っていますよね。
Googleは、数えきれないほどのWebページの中から、この人が本当に知りたいであろう「カレーライスの作り方」が書かれたページを厳選し、検索結果の上位に表示しようとします。
もし、検索結果の上位に「カレーライス 歴史」というページばかりが表示されたらどうでしょう?ユーザーは、求めている情報にたどり着けず、Googleに対して不満を感じてしまいます。
そうならないために、Googleは常に「ユーザーの役に立つか?」という視点で、Webページを評価し、順位を決めているのです。
Google検索順位が決まる3つの大きな要素
Googleは何百もの要素を使ってWebページを評価していると言われていますが、重要な大きな3つの要素があります。
1.コンテンツの「質」と「関連性」
これが最も重要な要素と言われています。
Googleは、「あなたの書いた記事が、検索したキーワードとどれだけ関連していて、どれだけ役に立つか」を徹底的に見ています。
関連性
検索キーワード(例:「カレーライス レシピ」)が、記事のタイトルや見出しにきちんと含まれているか?
キーワードに関連する言葉(例:「簡単」「本格」「具材」「作り方」)が本文にバランス良く使われているか?
質
他のサイトにはない、あなた独自の視点や経験が書かれているか?
読者が「なるほど!」と納得できるような、専門的で信頼性の高い情報が書かれているか?
最後まで読んでもらえるように、分かりやすく、読みやすい文章になっているか?
「とにかくキーワードをたくさん詰め込めばいいんでしょ?」と思われがちですが、それは間違いです。
不自然なキーワードの乱用は、Googleにスパムとみなされ、かえって順位が下がってしまうこともあります。
重要なのは、「読者が本当に知りたいことは何か?」を徹底的に考え、それに応える質の高いコンテンツを作ることです。
2.ユーザー体験(ユーザビリティ)
せっかく良い記事を書いても、読みにくいサイトでは意味がありません。Googleは、訪問したユーザーが快適にサイトを利用できるかどうかも評価しています。
ページの表示速度
ページが表示されるまでに時間がかかると、ユーザーはイライラしてすぐに離脱してしまいます。できるだけサクサクと表示されるようにしましょう。
スマホでの見やすさ
今や、検索のほとんどがスマートフォンで行われています。PCでしか見にくいサイトは、評価が下がってしまいます。
スマホでも文字が小さすぎず、ボタンが押しやすいなど、快適に使えるようにしておくことが大切です。
サイトの構造
読者が探している情報にたどり着きやすいように、カテゴリー分けや内部リンク(サイト内の他のページへのリンク)を整理しておくと、Googleも「このサイトは分かりやすい」と評価してくれます。
「とにかくキーワードをたくさん詰め込めばいいんでしょ?」と思われがちですが、それは間違いです。
不自然なキーワードの乱用は、Googleにスパムとみなされ、かえって順位が下がってしまうこともあります。
重要なのは、「読者が本当に知りたいことは何か?」を徹底的に考え、それに応える質の高いコンテンツを作ることです。
サイトの「信頼性」と「権威性」
「誰が書いた記事か?」というのも、Googleが重視するポイントです。特に、健康や金融など、人々の生活に大きな影響を与えるテーマでは、より一層厳しく評価されます。
信頼性
・書かれている情報が正確で、出典が明確か?
・運営者の情報(プロフィールなど)がきちんと記載されているか?
権威性
・その分野の専門家や、権威あるサイトからリンクを貼られているか?
・多くの人に引用されたり、SNSでシェアされたりしているか?
ブログであれば、自分の実体験や、独自の視点を交えて書くことで、他の誰にも真似できない「経験」という権威性を確立することができます。
なぜ検索順位は変動するの?変動のタイミングはいつ?
「頑張って作った記事が上位表示された!やったー!」と喜んだのも束の間、次の日には順位が大きく下がっている…なんてこと、ありますよね。
Googleの検索順位は常に変動しています。その変動には、大きく分けて3つのタイミングがあります。
日常的な小さな変動
Googleは、より良い検索結果をユーザーに提供するために、日々少しずつアルゴリズム(順位を決定するためのルール)を調整しています。
これは、Googleが「このキーワードで検索するユーザーは、もしかしたらこんな情報も知りたいんじゃないか?」と推測し、様々なパターンを試しているためです。
例えば、「ハンバーグ レシピ」と検索したユーザーが、レシピだけでなく「ハンバーグの付け合わせ」や「ハンバーグの歴史」といったページもよく見ていると分かれば、Googleはそれらの関連ページを少しだけ上位に表示させてみる、といったことを日々繰り返しているのです。
この日常的な変動は、数日〜1週間程度で落ち着くことがほとんどなので、一喜一憂せずに様子を見るのが大切です。
新規記事公開直後の変動
新しい記事を公開したばかりのときは、Googleもまだその記事を完全に評価しきれていない状態です。
記事が公開されてから、Googleのロボットがサイトを巡回し、記事の内容を読み込み、インデックス(データベースに登録)するまでに時間がかかります。
インデックス登録された後も、ユーザーの反応(どれくらいの時間読まれたか、他のページも見てくれたかなど)を見ながら、最適な順位を探っていくため、順位が不安定になりがちです。
一般的には、新規記事の順位が安定するまでに数週間〜数ヶ月かかると言われています。焦ってすぐにリライトするのではなく、まずはじっくりと様子を見ることも必要です。
コアアップデートによる大きな変動
年に数回、Googleは検索アルゴリズムを大幅に更新することがあります。これを「コアアップデート」と呼びます。
コアアップデートでは、これまでの順位の評価方法が大きく見直されるため、多くのサイトで検索順位が大きく変動します。
コアアップデートの目的は、常に「よりユーザーの役に立つ情報を上位に表示する」ことです。
過去には、質の低いコンテンツを大量生産するサイトの順位が下がったり、権威性のあるサイトが評価されたり、といった変化がありました。
もしコアアップデートで順位が大きく下がってしまった場合は、Googleが求める「質の高いコンテンツ」から外れてしまった可能性があります。
その場合は、
・記事の内容が、本当にユーザーの役に立っているか?
・オリジナリティはあるか?
・信頼できる情報か?
といった点をじっくり見直し、改善していくことが重要です。
まとめ
Googleの検索順位は、単なる裏技やテクニックで上げるものではなく、「ユーザーの役に立つかどうか」が最も重要な基準になっています。
順位が変動するのは当たり前。
その変化に一喜一憂するのではなく、ユーザーにとって良い情報を、わかりやすく、スムーズに届けるサイトを作り続けることが一番の近道です。
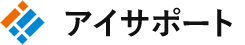
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)