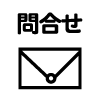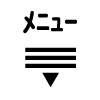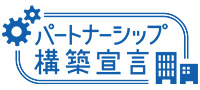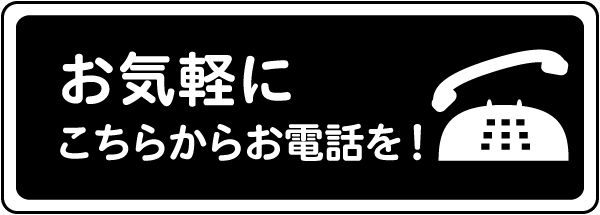ブログ
-

-
加工事例が必要な理由
-
加工技術が優れている企業でも、なかなか新規顧客を得ることができず、自分たちの技術をまだまだ広められていないという企業は少なくないでしょう。
ここでは、加工技術を表現するための加工事例公開が重要な理由についてご紹介していきます。加工事例が必要な理由
ホームページに加工事例を載せる理由としては、どのようなものがあるのでしょうか。
技術力をユーザーに表現できる
まずは、自社の技術力をユーザーに表現できるということです。
言葉で技術力があると表現しても、なかなか信ぴょう性がなく伝えることができません。Googleが求めるコンテンツになる
Googleは、ユーザーが求めるコンテンツを表現することが望ましいという考えを持っており、加工事例はユーザーが知りたい情報であったり、求めるコンテンツだったりするため、Googleが求めるコンテンツとなります。
SEO対策になる
つまり、Googleが求めるコンテンツになるということは、検索結果で上位表示を狙いやすくなるということになり、SEO対策になるということです。
加工事例の表現方法
加工事例はどのような表現をすれば良いのか、見ていきましょう。
1ページ1コンテンツ
加工事例を表現する時は、1ページ1コンテンツを意識し、1ページの中で沢山の事例を表現するのではなく、一つ一つにフォーカスし、1ページで表現することが大切です。
「沢山事例があるな」よりも、1つずつの事例を1ページで表現することで、ユーザーは見やすくなり、コンテンツに集中して見ることができます。ユーザーが求めているものを意識する
加工事例を表現する上で大切なのは、ユーザーが求めるものが何かということです。
それには、ターゲットの選定が必要であり、ターゲットに合わせて求められる加工事例を表現することが必要です。まとめ
ここまで、加工事例をホームページに表現する重要性についてご紹介してきました。
加工事例を表現することは、ユーザーからもGoogleからも良い評価を得ることができます。
-
-

-
施工事例が必要な理由
-
リフォーム会社や建築会社が顧客獲得のためにホームページを開設するというのは、もう当たり前のことですが、しっかりと成果に繋がっているでしょうか。
実は、ホームページに施工事例を載せることが、成果に繋げるポイントになります。
ここでは、施工事例の重要性についてご紹介していきます。施工事例、出していますか?
ホームページに施工事例は出していますか?
リフォーム会社などの多くのホームページで施工事例が出ておらず、もったいないホームページをよく見ます。
自分たちが出来ることや、得意としていることは記載していても、実際の施工事例を疎かにしているホームページはなかなか成果に繋がりにくいでしょう。施工事例が重要な理由
施工事例が重要な理由を見ていきましょう。
SEO対策になる
まずは、SEO対策になるということです。
Googleは、検索順位を決めるアルゴリズムの中で、重要なのは「ユーザーにとって価値のあるコンテンツ」というものがあります。
ユーザーは、施工事例などを見ることでイメージが付きやすくなるため、大事なコンテンツという位置づけになり、ユーザーが満足するものはGoogleも満足することになります。コンバージョン(問い合わせ)につなげやすい
ユーザーが満足し、不信感や不安が無くなると、コンバージョン(問い合わせ)に繋がりやすくなります。
つまり、施工事例を出すことで、見込み客の獲得をしやすくするということです。施工事例が出ていないHPは…
施工事例が出ていないHPは、どのような仕事をしているかわからないことや、実績があるのが不安に思うユーザーもいるため、なかなかコンバージョン(問い合わせ)に繋がりにくく、成果の出るホームページの運用ができていないケースが多いでしょう。
まとめ
ここまで、施工事例はホームページに必要であるということをお伝えしてきました。
出しても良い施工事例がある場合には、積極的に表現するようにしましょう。
-
-

-
展示会営業を効率化したい
-
商品やサービスを販売する際に、展示会を利用して集客する企業も少なくないでしょう。
特にITツールや、自社開発した製品を世に出したいと思ったとき、展示会というのは大きな販路になるでしょう。
そこで、今回は展示会営業を効率化し成果を上げるためのポイントをご紹介していきます。展示会営業は中長期的に考えよう
展示会営業を行う上で、大事な考え方を先にご紹介すると、展示会営業は単発的なものではなく、中長期的な営業活動ということを認識することが必要です。
その場で良いと思っても基本的には契約に繋がるまでに長い期間を要するため、中長期的な視点で活動をすることが重要です。展示会営業を成功させるコツ
展示会営業を成功させるためのコツについて見ていきましょう。
定期的なフォロー
展示会営業では、展示会で集めた名刺などの顧客リストから、定期的にフォローすることが重要です。
「興味がなさそうだから連絡しないでおこう」というのは展示会をした意味がありませんので、興味がなさそうな方にもしっかりと定期的にアプローチをすることが必要です。
そもそも、興味がない人は展示会に来ないでしょう。顧客のセグメント
セグメントとは「区分け」のことです。
見込み客の興味の高さからランク付けするなど、セグメントして顧客にアプローチすることで、優先順位をつけて営業活動ができるため、生産性を高めることができます。顧客リストを集めるには
顧客リストを効率的に集めるには、展示会において目立つことと、情報提供の質を高めることが必要です。
パネルやブースの工夫
展示会で足を止めてもらうためにはパネルやブースを工夫しなければなりません。
足を止めやすくなるように、目立たせることや、ブースの形を考えることが必要です。
足を止めてくださいと言っても顧客は素通りしてしまうので、興味を持たせる何かを置いたり、パネルに訴求効果の高いキャッチ―を考えたりするなど工夫をしましょう。顧客に価値ある情報提供
顧客に価値のある情報を提供するということは、顧客が興味のあるものを提供するということです。
例えば、SEOに対してのツールを提供している企業であれば、「SEOに欠かせない10のポイント」などの資料を配るなど、情報提供することで興味を持ってくれるでしょう。まとめ
ここまで、展示会営業を成功させるポイントについてご紹介してきました。
展示会営業において大切なのは中長期的に考えるということと、顧客リストをたくさん集めるということです。
顧客リストを集めたあとは、質の高い顧客から優先的にアプローチするなどの工夫をすることが良いでしょう。
-
-

-
自社サイトの個別のアクセス状況がわかる
-
Webサイトからのコンバージョンを高めるため、Web担当者はさまざまな改善を行っていることでしょう。
これまではアクセス解析や離脱率などの解析、改善が主なWeb解析の方法でしたが、現在では個別にアプローチするという手法が用いられてます。
その手法の一つに個別アクセス状況の把握があります。
ここでは、個別のアクセス状況が確認できるという点にフォーカスしてご紹介していきます。アクセス解析、できていますか?
Webのアクセス解析をする際、Googleアナリティックスやサーチコンソールを利用して、アクセス状況の把握やキーワードの分析などで活動を止めていないでしょうか。
今では、サイトに訪れたユーザーを個別に識別して行動を確認することができるようになっています。
質の高いアプローチをするためには、このような個別のアクセス状況の確認が欠かせないものとなっています。個別のアクセス状況がわかるメリット
個別にアクセス状況がわかるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
ターゲットごとにアプローチできる
個別にアクセス状況が分かることのメリットとして挙げられるのは、それぞれの個別のターゲットごとにアプローチ方法を変えられるということです。
例えば、メールマガジンを配信しているユーザーがメールを開封し、記載されているURLからサイトに訪れた際に、そのユーザーに向けて次のアクションを取ることができます。
メールに記載されているURLから訪れた人がどれくらい滞在し、何に興味があるかを把握することによって、ユーザーが求めるものや課題が見えてくるため、効果的なアプローチが可能になります。質の高いアクションができる
何もわからずにアプローチするよりも、顧客が抱えている課題や、興味を持っているものなどが分かることで、どのようなアプローチをするべかが見えてくることと、それぞれどのようなフェーズにいる顧客かを把握することで、質の高いアプローチができます。
ツールの利用でさらに最適化を
質の高いアプローチをする方法として、マーケティングツールを利用することも一つの方法です。
先ほどのサイトに訪れた方に向けて効果的なアプローチをするなら、MAツールやヒートマップツール、ユーザー行動観察ツールなどを利用することがおすすめです。まとめ
ここまで、アクセス解析について、個別のアクセス状況がわかることと、それに対してどのようなアプローチをするべきかなどをご紹介してきました。
マーケティング活動において、「面」から「点」に変わってきた現代、このような個別アプローチは欠かせないマーケティング活動となります。
-
-

-
展示会でもらった名刺の活用方法
-
どのような企業でも、名刺をもらう機会は多いでしょう。
営業や社長も含め、名刺は一元管理しておくべきですが、なかなかそのようなことはわかっていても出来ていない企業が多いでしょう。
名刺を活用するメリットを感じていないため、そのようなことになると思いますが、ここでは名刺を利用した活用法についてご紹介していきます。展示会でもらった名刺、そのままじゃありませんか?
展示会などを開催したとき、多くの名刺をもらうことでしょう。
しかし、その名刺は活かされているでしょうか。
展示会が終わったあと、数週間は連絡を取っていても、その後は定期的な連絡やフォローができているでしょうか。出来ていない理由の一つに、名刺をデジタル化していないということが挙げられます。名刺の活用法
名刺を活用するにはどのような方法が良いのでしょうか。
ホームページへの誘導
展示会などでもらった名刺を活用する方法の一つに、ホームページへの誘導があります。
例えば、メールなどでホームページへ誘導し、そこから顧客への認知を高めたり、情報提供することで、繋がりを持ち続けたりするということができます。お知らせメールでナーチャリング
お知らせメールやメールマガジンを配信することで、顧客とつながり続けたり、情報提供し続けたりすることで顧客に知識を付けさせ、自社の商品やサービスが素晴らしいものであるということを認知してもらうということができます。
これがナーチャリングであり、ナーチャリングをする上で、名刺のメールアドレスを活用することはとても効果的なことと言えるでしょう。名刺をデジタル化するには
ホームページの誘導やナーチャリングする上で必要になるのはメールアドレスです。
このメールアドレスが名刺に記載されているものをそのまま使うだけだと、効率が悪いですし、時間が掛かるため中々続かないでしょう。
このようなことを避けるため、名刺をデジタル化することがおすすめです。
デジタル化するためには、LINE株式会社が提供している「myBridge」やSanSan株式会社が提供している「Eight」、ウォンテッドリー株式会社が提供している「Wantedly People」などがあります。まとめ
ここまで、名刺を活用する方法についてご紹介してきました。
名刺はデータ化していないと、活用しづらいため、活用するためにまずはデジタル化することと、会社単位で、一元管理することがおすすめです。
-
-

-
マーケティングオートメーションとは
-
デジタルマーケティングが中心となっている現代のマーケティングでは、定量化されたデータ分析から顧客の見える化などができることから、マーケティング活動の手段も日々変化しています。
その中でも、マーケティングオートメーションという言葉は、マーケティングを担当している方なら聞いたことがある言葉の一つでしょう。
ここでは、マーケティングオートメーションについてご紹介していきます。マーケティングオートメーションって何?
マーケティングオートメーションとは、その言葉通り、マーケティング活動、つまり営業から購買、リピートされるまでの活動を自動化するというツールです。
多くのマーケティングオートメーションツールが世の中で提供されており、MAツールと呼ばれています。マーケティングオートメーションでできること
次に、マーケティングオートメーションでできることを見ていきましょう。
リードジェネレーション
リードジェネレーションとは、見込み客の獲得、つまりお問合せや資料請求、来店などを獲得するための活動を言い、非デジタルのリードジェネレーションでいうと、チラシの手配りなどもそれにあたります。
リードナーチャリング
リードナーチャリングとは、顧客の育成です。
現代のマーケティングでは、顧客に成長してもらい、業界や分野、製品についての知識を増やすことで、顧客自らが「欲しい」と思い、行動させるために必要な「教育」が必要です。リードクオリフィケーション
見込み客の中でも「今すぐ客」と「これから客」などに分類されますが、このような顧客のセグメント(区分け)を行うことをリードクオリフィケーションと言います。
このように、マーケティングオートメーションでは、デジタルマーケティング活動に必要となるリードジェネレーションやナーチャリング、クオリフィケーションを得意としています。
マーケティングオートメーションを利用する際のポイント
マーケティングオートメーションを活用するためのポイントとしては、マーケティング活動全てをこのツールが行ってくれるというわけではないことを理解することです。
人がやらなければならないことや、管理しなければならないことなどがあるため、マーケティングオートメーションに何を求め、どこをやってもらうかを明確にすることが成功のポイントです。まとめ
ここまで、マーケティングオートメーションについてご紹介してきました。
リードジェネレーション・ナーチャリング・クオリフィケーションなどは、デジタルマーケティングにおいて重要な活動であり、それらを補佐する役目としてMAツールを利用されると良いでしょう。
-
-

-
ECサイトとモールの比較
-
ネットショップをはじめたいと思ったとき、検討するのは「自社ECサイト」か「モールの利用」ではないでしょうか。
ここでは、自社ECサイトとモール、それぞれのメリットについてご紹介していきます。ネットショップを始めるなら自社EC?それともモール?
ネットショップを持つとき、自社ECサイトかモールでは、どちらが良いのでしょうか。
それは、扱う商品や、どこまで自分でやりたいかによって異なります。自社ECのメリット
自社ECサイトを持つメリットとしては、オリジナル性を持たせることや、利益率が高いということが挙げられます。
オリジナル性を持たせられる
自社ECサイトは、モールではできないようなオリジナル性を持たせることができます。
モールを利用するとある程度運営側により制限が掛かり、機能性やデザイン性の面でやりたくても出来ないことがありますが、自社ECサイトでは不可能なことは基本的にはありません。利益率が高い
モールへの出品では手数料が掛かりますが、自社ECサイトの運営では販売手数料などがないため、一つずつの商品に対しての利益率を高めることができます。
モールを利用するメリット
モールを利用するメリットとしては、集客力やはじめやすさという点が挙げられます。
集客力がある
モールを利用することで、モールのネームバリューが高いため、集客力があります。
自分たちのサイトや商品に興味がないユーザーもモールに訪れるため、販売機会を増やすことができます。簡単に始められる
モールでは、テンプレート型のページ作成ができるため、簡単にネットショップを持つことができます。
最短で1日でネットショップを始めることができるため、手軽に始めたい方にはおすすめです。自分で作り上げたいなら自社ECサイト
マーケティングという視点で見ると、集客しやすいのはモールですが、オリジナル性を持たせたり、独自のブランディングをしたいと思ったり、マーケティングをしたいという場合には、自社ECサイトがおすすめです。
0から作り上げて自分だけのネットショップ運営がしたい場合には、モールではなく自社ECサイトを持つと良いでしょう。まとめ
ここまで、ネットショップをはじめるにあたり、自社ECサイトが良いのか、モールを利用したら良いのか、それぞれのメリットをご紹介してきました。
ネットショップの需要は高まっており、これからもネットを利用した買い物をするユーザーが増加していく傾向にあるため、是非この機会にネットショップを始めてみてはいかがでしょうか。
-
-

-
ダウンロード資料はなぜあるのか?メリット
-

ホームページで問い合わせを増やすため、「ホワイトペーパー」の利用を検討されている方も少なくないでしょう。
ここでは、ダウンロード資料であるホワイトペーパーを利用するメリットについてご紹介していきます。ダウンロード資料を使うメリット
ダウンロード資料を利用するメリットはどこにあるでしょうか。
ユーザーとの接点を多くする
まずは、ユーザーとの接点を多くするというメリットがあります。
マーケティング活動で大切なのは、ユーザーとの接点を多く持つことで、それにはただホームページを訪問してもらうということだけではなく、資料のダウンロードをしてもらうことで、接点を多く持つことができます。ユーザーの情報を与える
ユーザーに対して重要な情報や、役立つ情報を提供する方法として、資料のダウンロードは有効です。
ホームページだけでは表現できない情報を、ダウンロード資料にて提供することが望ましいでしょう。最終的な売上に繋がる
ユーザーが満足し、接点を多く持ち信頼関係を作ることで、コンバージョンに繋がり、結果的に会社の売上や利益につながっていきます。
ダウンロード資料のポイント
ダウンロード資料にはどのようなものが良いのでしょうか。
PDF形式にする
ダウンロード資料でユーザーに情報を提供する時には、PDFファイルでの提供を行いましょう。
WordやExcelは開けない方もいますし、スマホで見る方などにもPDFは最適なのでPDFファイルにするようにしましょう。メールアドレスを入力してもらう
ダウンロードされる際に、誰にでも簡単にダウンロードしてもらうのではなく、メールアドレスなどの顧客情報を得るようにしましょう。
そうすることで、次のアクションを起こすことができます。まとめ
ここまで、ダウンロード資料の活用についてご紹介してきました。
ダウンロード資料をホームページで提供することは、ユーザーだけではなく、提供側にもメリットが多くありますので、是非ホームページをお持ちの企業はダウンロード資料を活用しましょう。
-
-

-
多いメールトラブルの切り分け方法
-
仕事をしていても、お家でも、メールのトラブルって多いですよね。
今回は、トラブルの多いメールについて、トラブル解決法をご紹介していきます。メールが使えない…原因は?
「メールが突然使えなくなった!」「昨日までは使えていたのに…」
こんなトラブルが発生したことはありませんか?
メールは突然使えなくなるということが多く、その原因は様々です。
大切なのは、原因を特定することです。原因を特定する方法
メールが使えなくなった原因はどこにあるのでしょうか。
原因を特定する方法をご紹介していきます。メールが使えない原因を切り分ける
まずは、メールが使えなくなった原因を特定することが必要であり、その要因は様々であるため、原因を切り分けて考えていくことが必要です。
まずは、以下のような点を抑えると良いでしょう。
・メールの受信ができているのか
・メーラーは立ち上がるか
・インターネットは接続されるか
・メールが使えなくなる前に普段やらないことをしたか
・メールの送信だけが問題なのか
これらを抑えておくことで、わかることは、
・そもそもインターネットがつながらない→メールの問題ではない
・メールの受信はできる、送信ができない→送信メールに問題あり(添付ファイルなど)
・メールを使う前にアプリをインストールした→アプリやセキュリティの問題かも
このような問題を区分けすることができます。どうしようもない原因は
メールが使えない原因を特定できても、自分たちではどうしようもない問題もあります。
それは、メールを受信・送信しているサーバーがダウンしていることや、パソコン本体のトラブルなのです。
そのような場合には業者に修理を依頼することや、サーバーが直るのを待つしかないでしょう。まずは、原因を特定しよう
メールが送受信できなくなったとき、一番に行うことは、原因を追究することです。
原因を特定できれば解決策が見つかりますが、そのためには原因の区分けが必要です。まとめ
ここまで、メールのトラブルについて、解決方法をご紹介してきました。
まずは、メールのトラブルがあったときは、原因を区分けすることから始めてみましょう。
-
-

-
CMSの種類
-
ホームページを構築しようと思ったとき、ホームページを構築するツールとして、CMSを検討している方も多いでしょう。
ここでは、CMSとは何か、その種類についてご紹介していきます。CMSとは
CMSとは、コンテンツマネジメントシステムというツールで、ブログを簡単に書いて投稿する機能などがついているツールで、世の中に多くのCMSが存在します。
CMSにはオープンソースと独自開発型がある
CMSには大きく分けてオープンソースタイプと、独自開発タイプがあります。
オープンソースとは
オープンソースとは、自由に利用しても良いというツールのことで、WordPressなどはこのタイプです。
日本のCMSの7割8割はこのタイプと言われており、メリットは多くのユーザーが利用しているので、ノウハウ提供なども各自が行っているという点があります。
一方、誰でも使えるツールとなるため、セキュリティの面においては、厳しい目で見ている方もいます。独自開発型とは
独自開発型とは、その名の通り独自開発しているCMSで、企業が独自で開発し、有償などで提供しているツールを指します。
例えば、WiXやJIMDOなどは独自開発ツールですが、WiXは無料からでも利用できます。CMSの選び方は?
CMSを選定する時、オープンソースが良いのでしょうか、それとも独自開発型が良いのでしょうか。
答えはどちらとも言えないという部分あり、その理由はそれぞれ強み弱みがあり、企業ごとでその強みや弱みを重要視するポイントが違うからです。
例えば、セキュリティ面を重要視したい方は、独自開発型の方が、セキュリティ対策がされていることが多いですが、費用面でいえばWordPressなどのオープンソースを利用すれば無料で利用できます。まとめ
CMSの種類について今回はご紹介してきましたが、企業がCMSを利用してホームページを開設する際には、選定ポイントとして、自社がどの部分を妥協できないかというポイントを絞ることが必要です。
セキュリティなのか、価格なのか、構築のしやすさなのか、それぞれの企業で検討してみると良いでしょう。
-
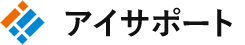
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)